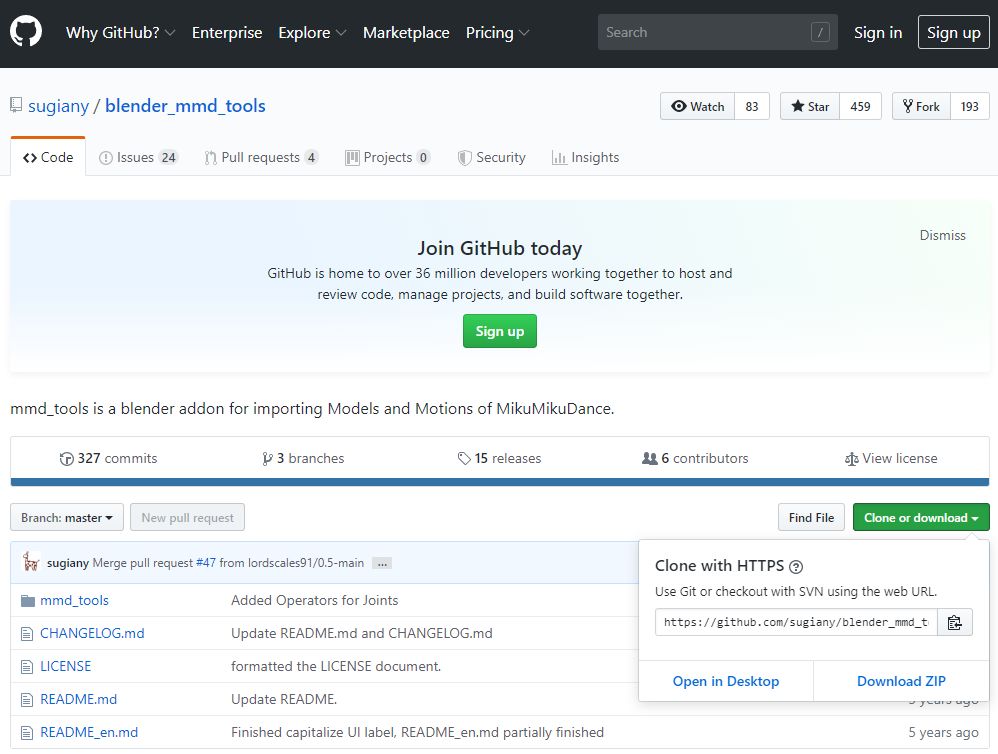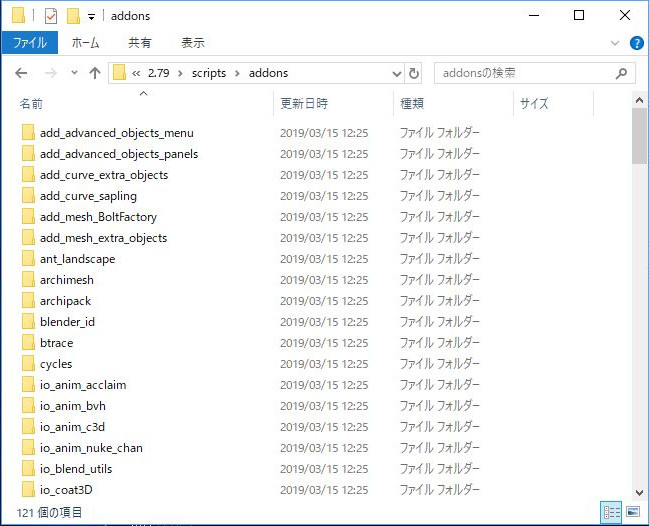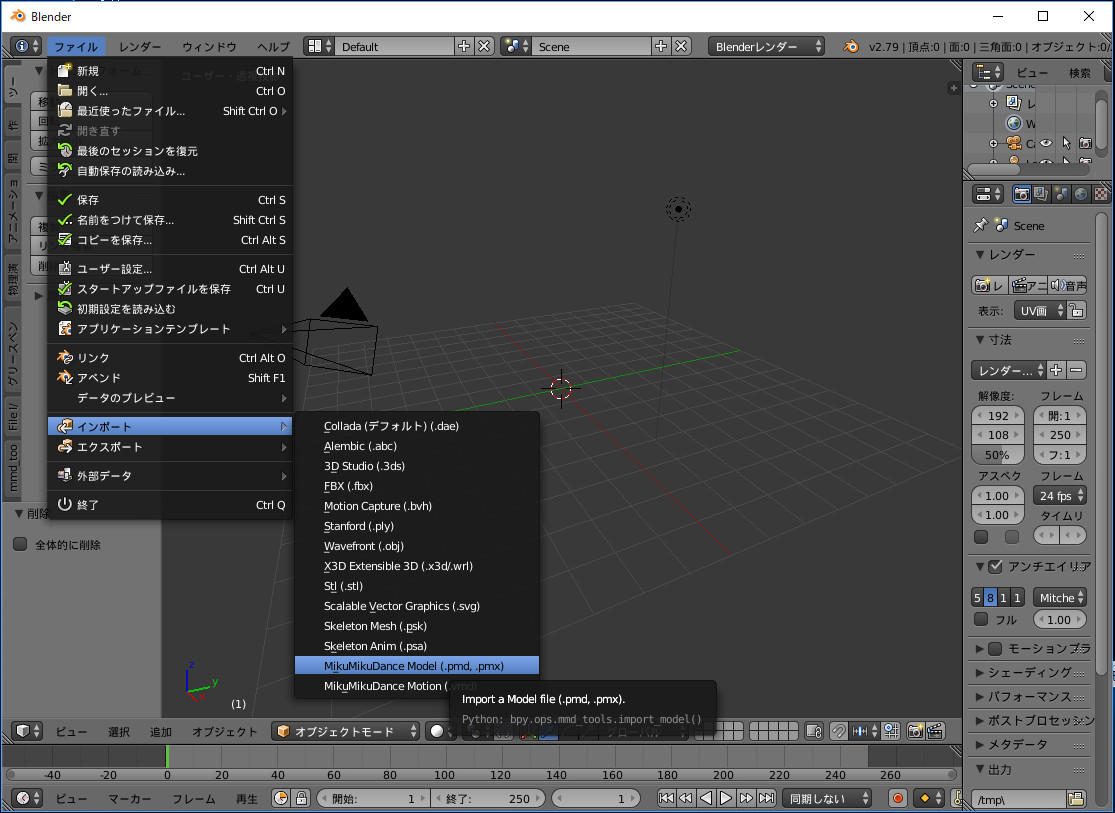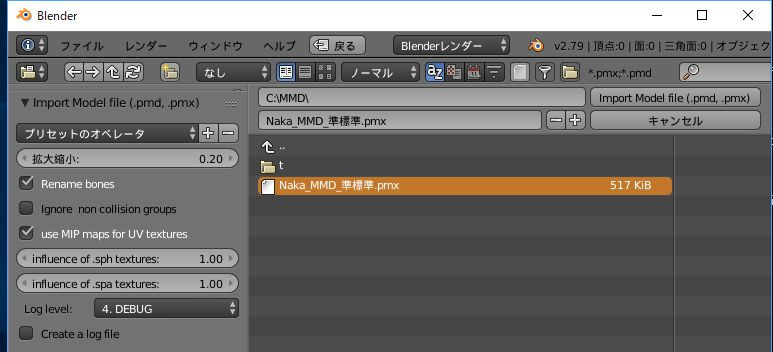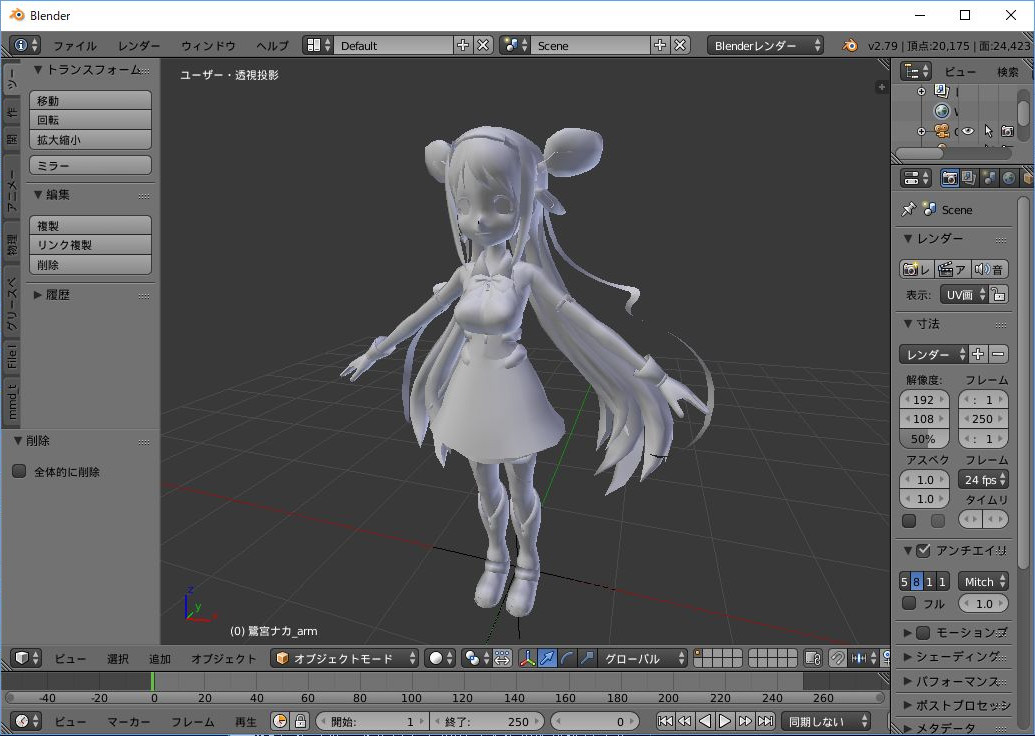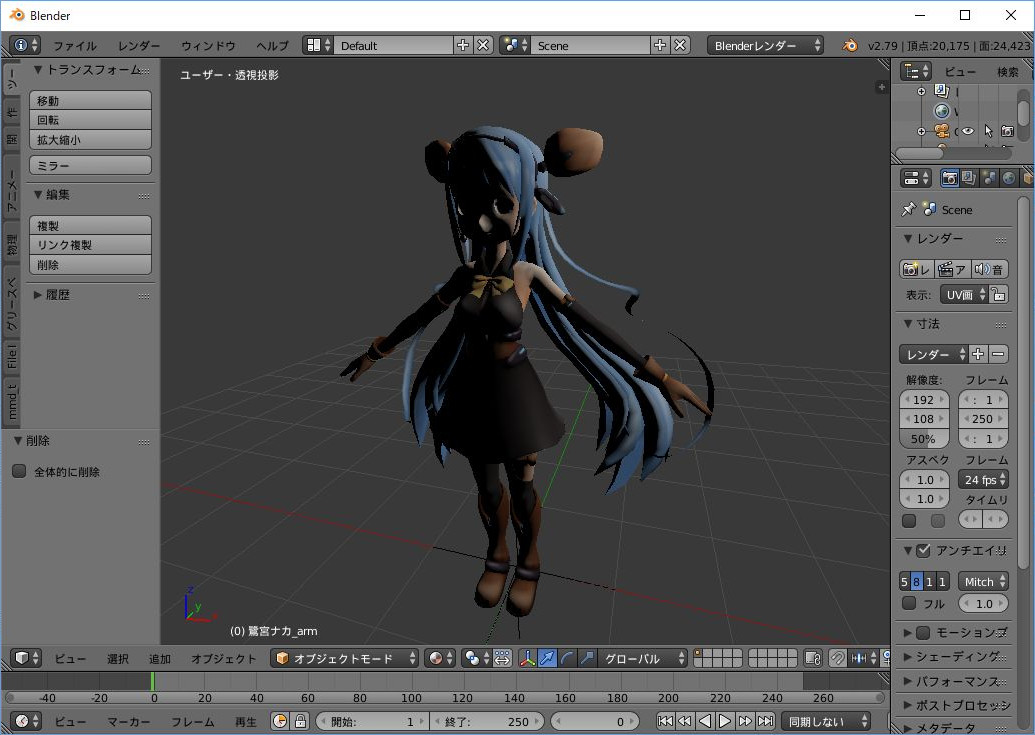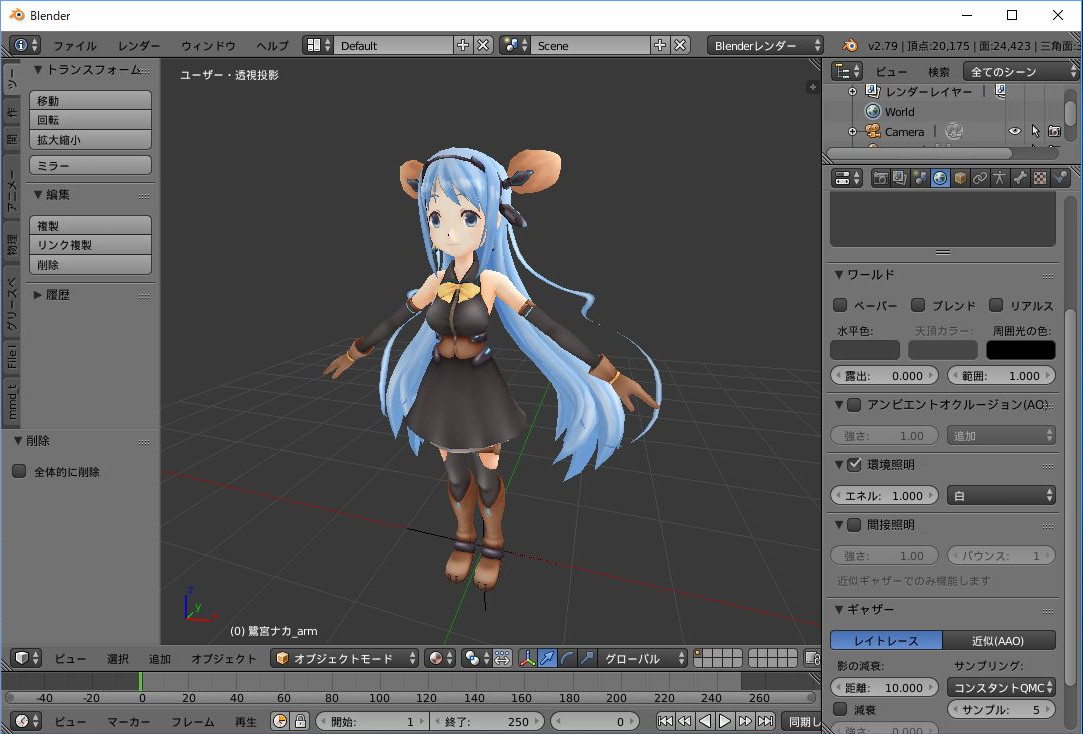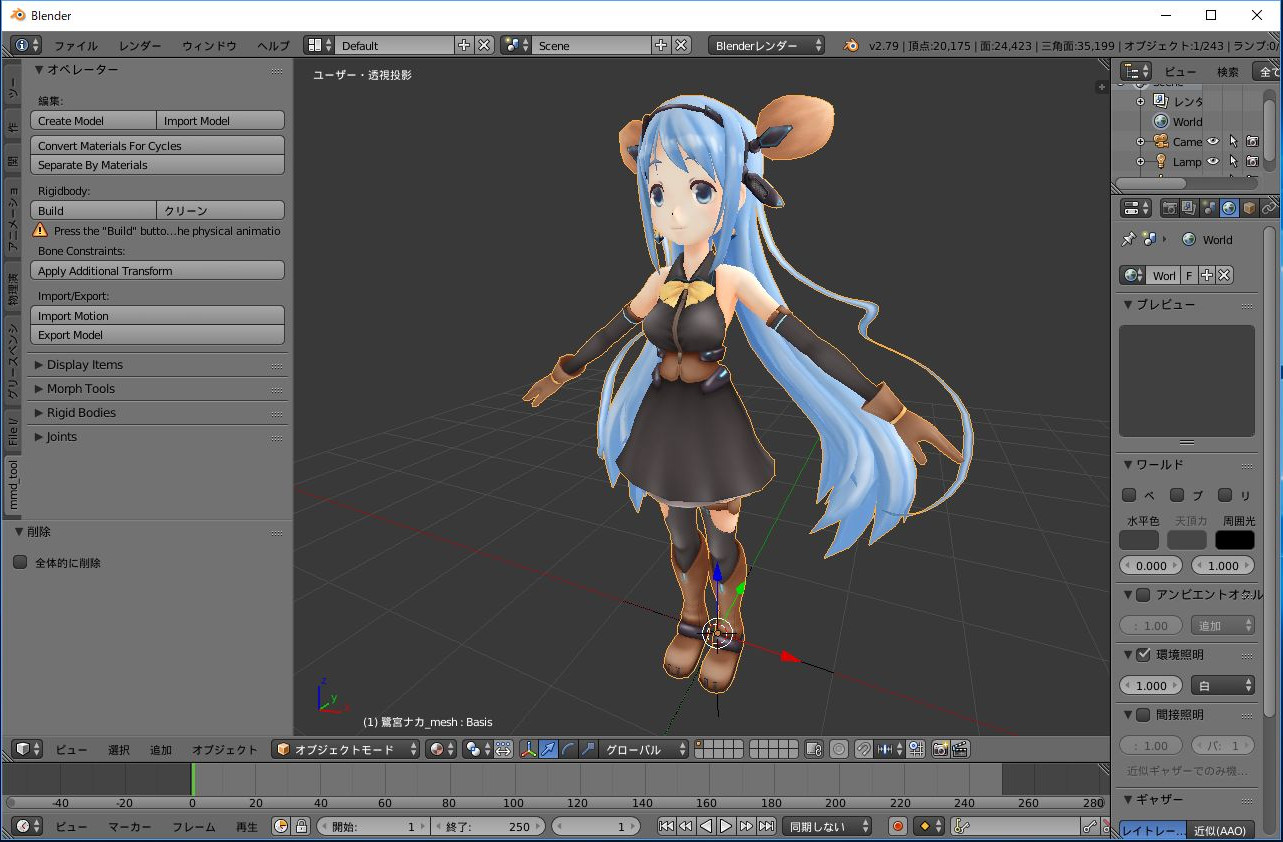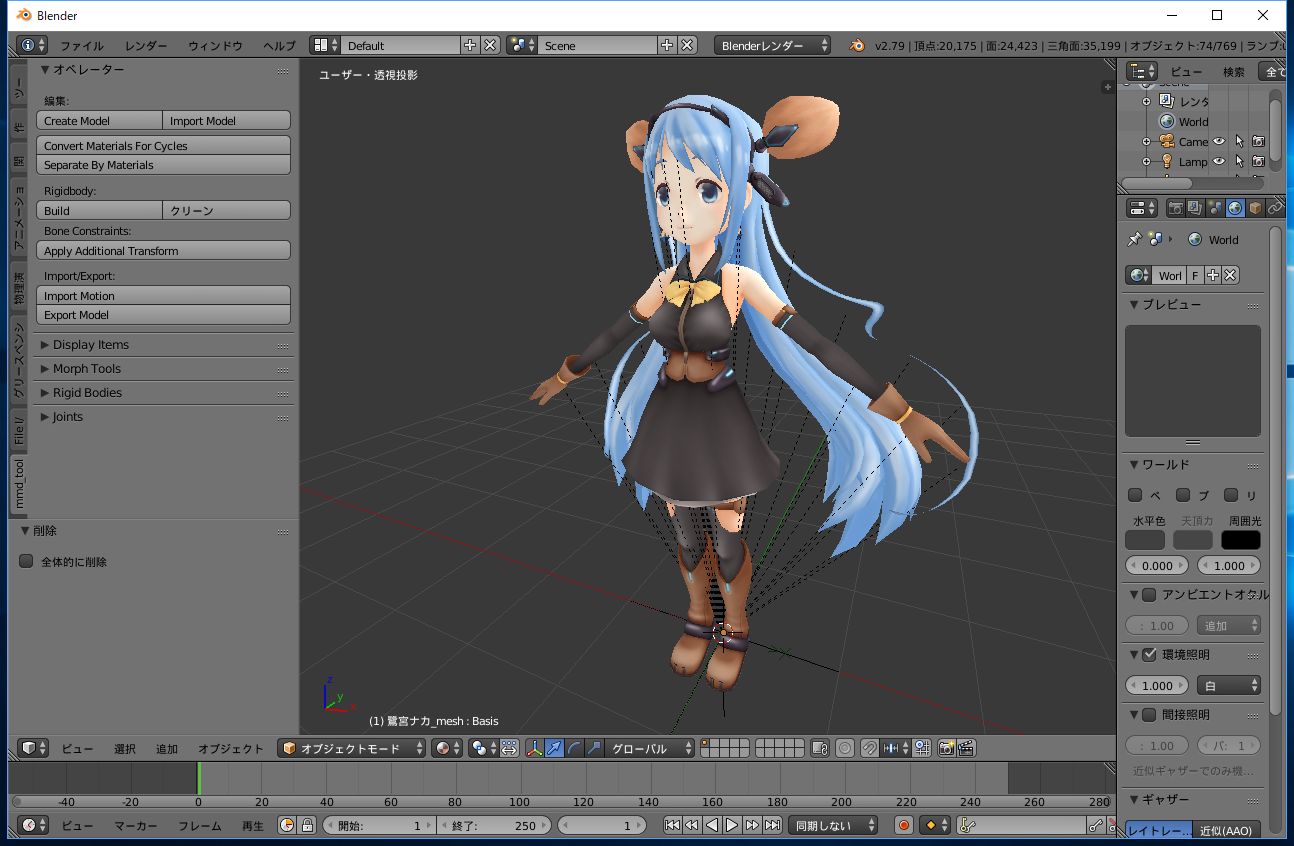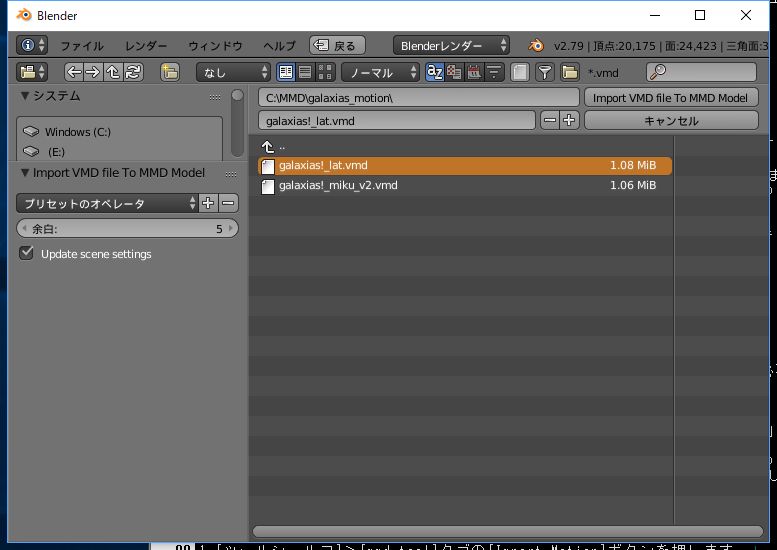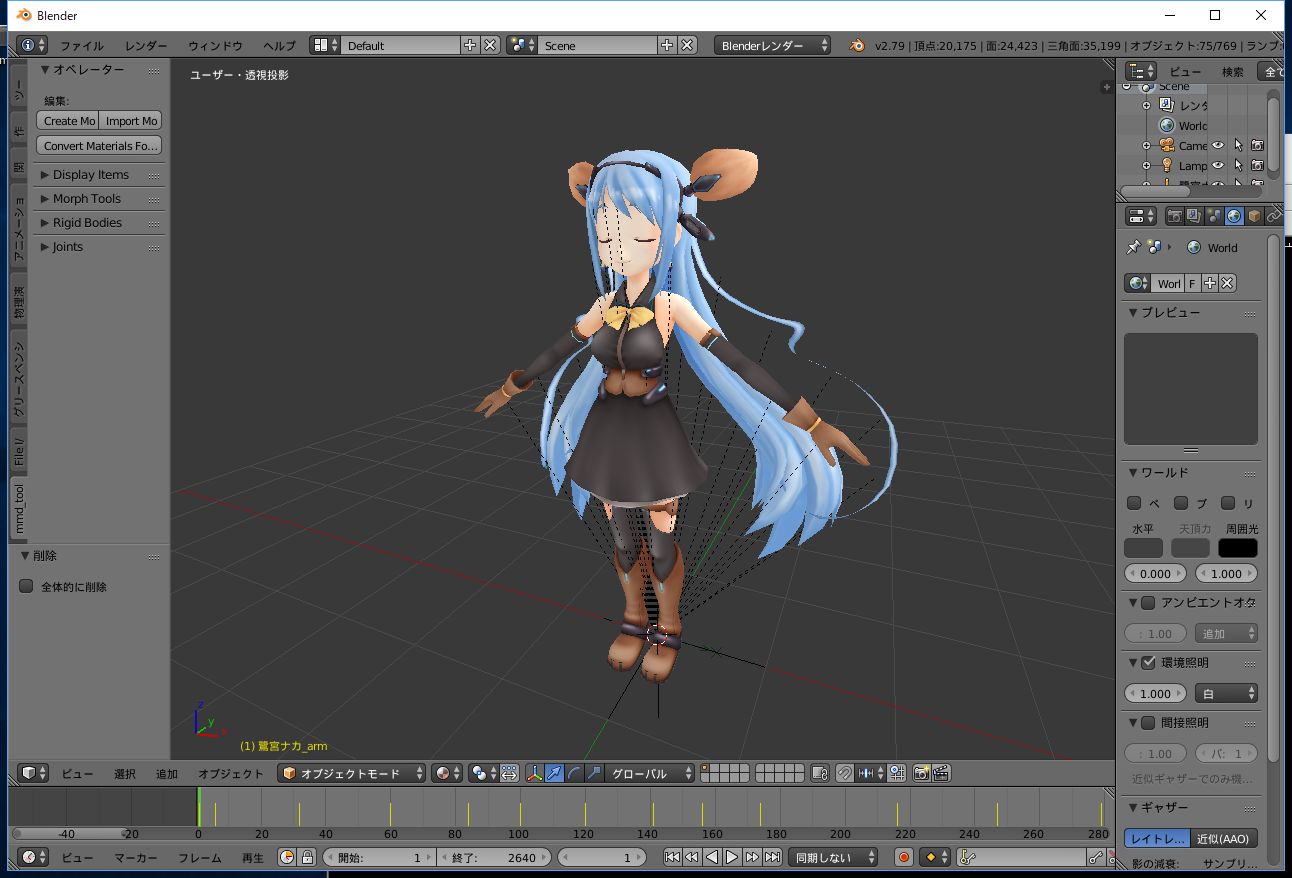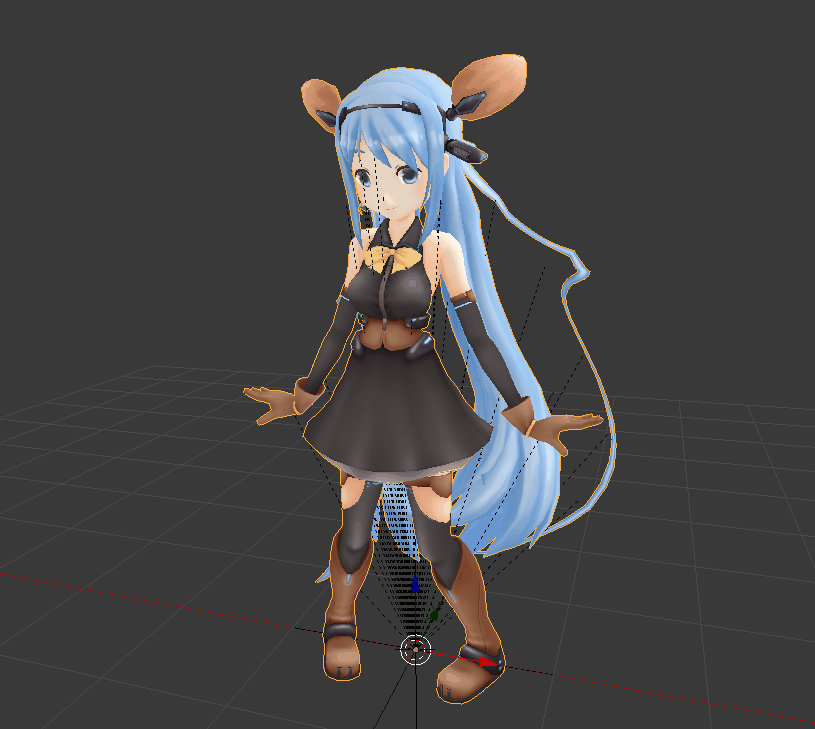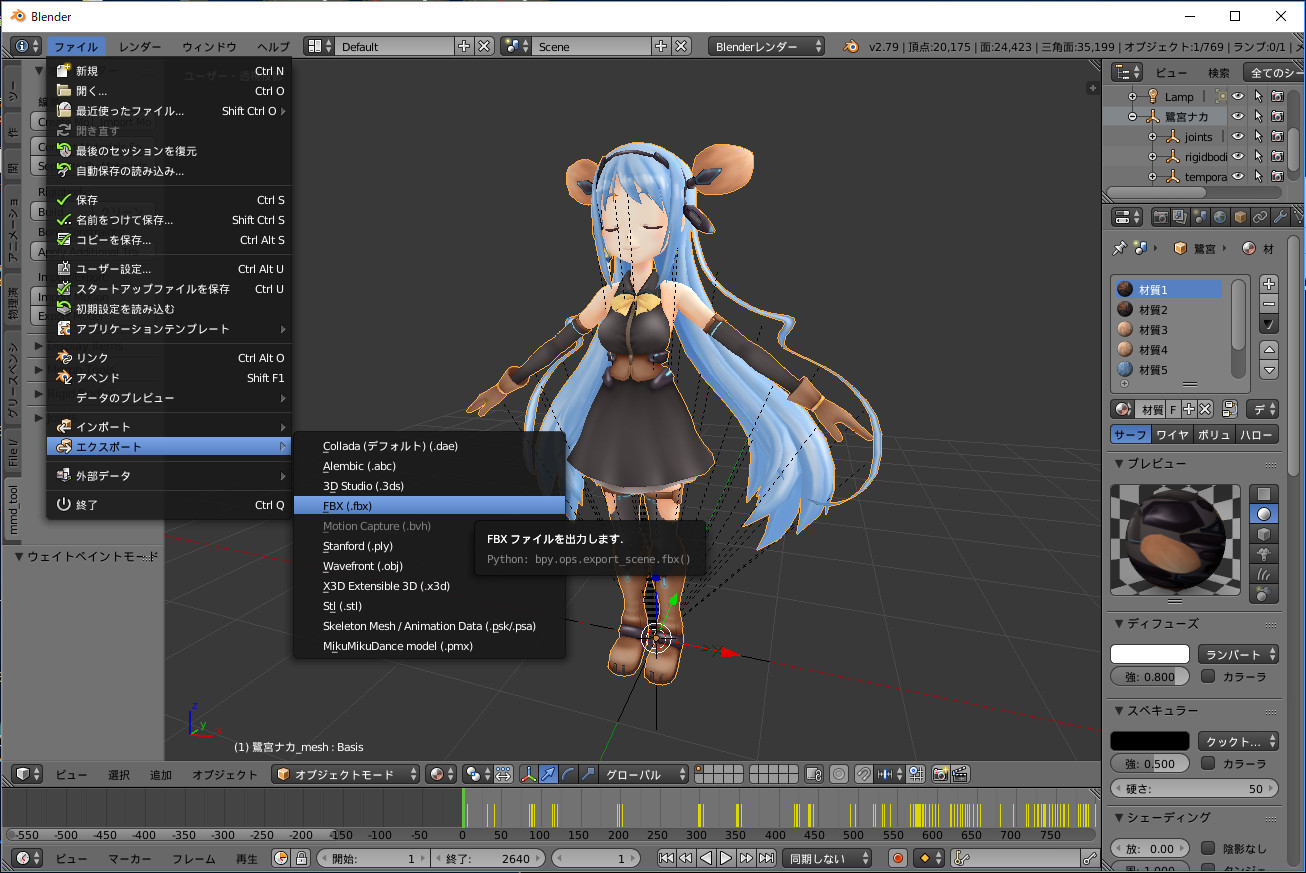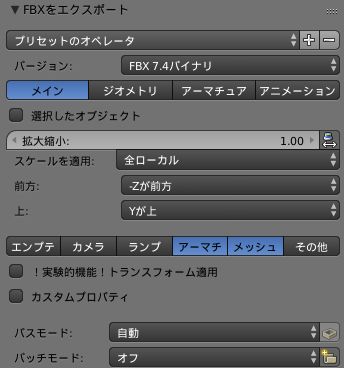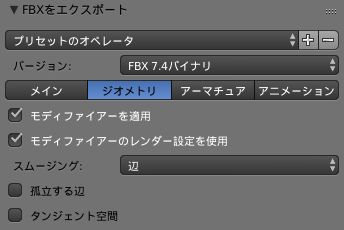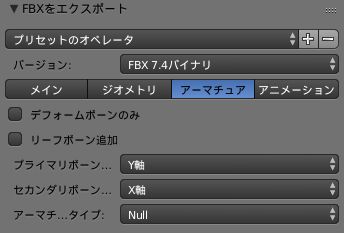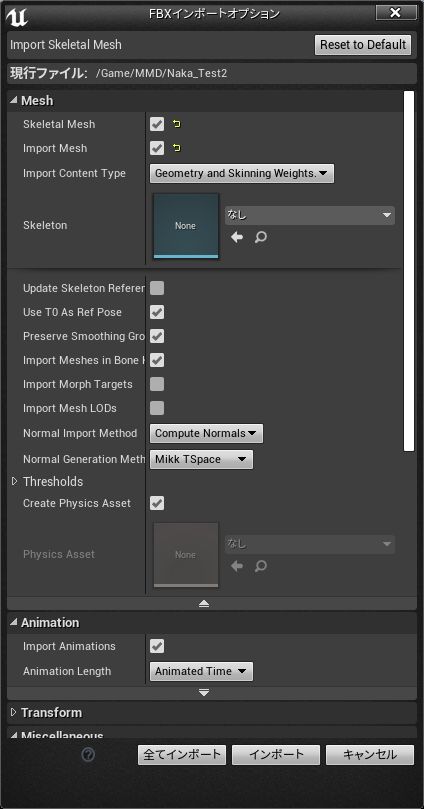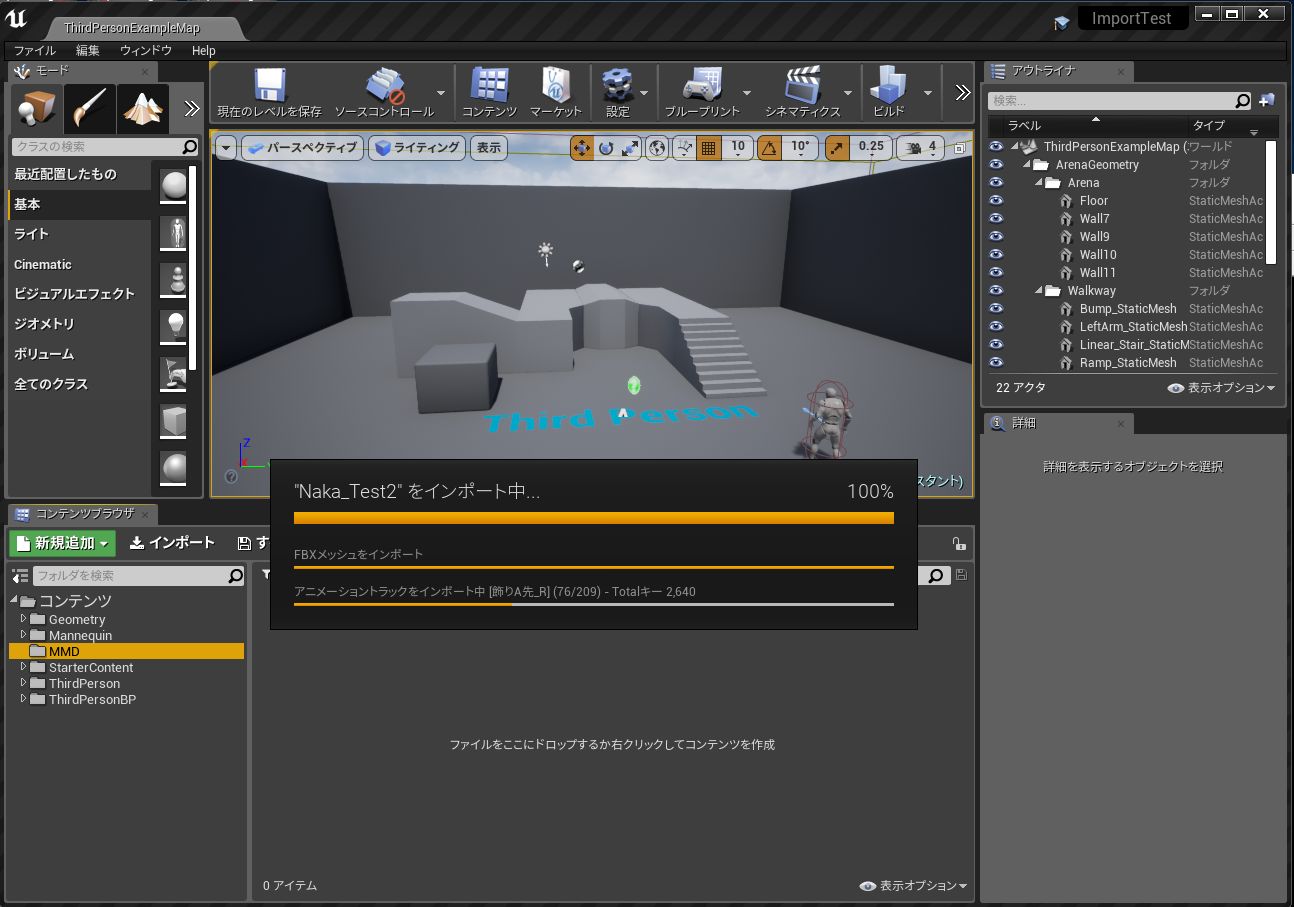※この記事は、2009/1/9に参加したARGイベント
「ぼくらのシモキタストーリー」のレポートです。
「ARGってなによ?」という方は、昨日の記事をご覧下さい。
※当日の内容を細かく書いているため、多分にネタバレを含みます。
なので、本文は閉じておきます。下の「→Read more…」をクリックすれば開かれます。
※本文は、主にプレイヤーキャラクター視点で書かれています。
グリーンの文字は、ゲームクリア済みの俯瞰した視点で書かれています。
※かなり記憶に頼って書いているので、不正確な部分があるかもしれません。
(特にセリフとか)
—–
EXTENDED BODY:
================================
1/7
天狗まつりの実行委員会の祐介からメールが届く。
祐介、沙織、哲郎が実行委員をしている「ぼくらのシモキタストーリー」
というイベントのフライヤーが荒らされてしまった、とのこと。

何者が?何のために?
3人で相談してまた連絡してくれるらしい。
1/8
再度祐介からのメール。またフライヤーが改変され、今度はお札のようなもののみになってしまった。

「天狗参上」と書いてあるように見える。まるで暴走族だなw
明日1/9の14時に、下北沢の真竜寺で作戦会議を行うとのこと。
1/9
一緒に応募した友人Kと共に、13:30頃下北沢に到着。
真竜寺に向かう道すがら、例の天狗のお札を何枚か見つける。

真竜寺には巨大な天狗の面のオブジェクトが!目立つなあ…。
でも主に歩く通りからは脇に入ったところなので、今まで全く存在に気付かなかった。

ARGの用途として下北沢の地域振興、という意味では
こういった何気ない発見によってきちんと寄与していると言える。
今回のイベントで、しばらく足が遠のいていた下北沢に
また興味を持つことができた。
そのオブジェクトの前には荒らされ壊れたテーブルが。
恐らく天狗まつり実行委員会のものなのだろう。
しかし実行委員会の人たちの姿は見当たらず。
ポツポツ集まっていた参加者達がテーブルの上の文章を眺めている。

どうやら「天狗」を名乗る人物からの挑戦状のようだ。文章を縦読みすると
「てんぐまつりはここからはじまるぞ いいんちょう」となる。
祐介たちを探すべきか悩むが、まだ14:00になっていないし、
参加者も全員が集まり切っていないので待機。
そうこうしているうちに祐介からメールが。
どうやら委員会の3人は「天狗」が事件を起こそうとしているので駅に向かったとのこと。
見て欲しいものがあるというので、三手に別れて駅に向かうことに。
私のCチームは不参加が出たため、私と友人Kの二人のみ。
祐介のメールの指示に従って、Eチームと共に北口のampm前に向かった。
「こんにちは!僕哲郎です!」
ampm前で待ち構えていた青年の第一声は、あまりにも爽やかな挨拶だった。
なんという爽やかさ…これが若さか。
否、私が彼くらいの時はネクラで…と、そんなことはどうでもいい。
哲郎君によると、駅前に駆けつけた彼らは不審な封筒を見つけたらしい。
中には天狗からの問題。「1.2.3.4.5.6.7.5.6」という数字が並んでいる。
問題文は忘れちゃいました☆サーセンw
それと、看板部分が塗りつぶされた7枚の写真。
それぞれにヒントも書き添えられている。番号と、「○番目のアルファベット」など。
最後にルートの書かれた地図。
問題の意味がまだ分からないが、ひとまずルートをたどってみることに。
2ルートあるので、近場の単純な方から回る。
途中、工事現場警備のおばちゃんに「ここにあるよ!」
と声をかけられてビックリ!
指差す方を見ると、天狗マークに「沢」の文字が。
な…何者だったんだ…?天狗の手のものか?
まあヒントをくれたから良しとしよう。我々は急いでいるのだ。
おそらくはデバッグプレイ、あるいは問題設置の様子を見ていて
なんらかのイベントを行っていることを察してくれたのだろう。
偶然だったのかもしれないが、それまで我々だけで
勝手にやっていた感のあったこのイベントに、
現実世界が深くリンクしたと感じた瞬間だった。
一つ目のルートを回り終え、集まった文字は「1.下」「2.北」「3.沢」。
なるほど、どうやら全部集めれば何らかのワードになりそうだ。
二つ目のルートはちょっと変則的な形だが回ってみる。
哲郎くんが、要所要所で下北のオススメのお店とかを教えてくれる。
途中一つを見落としたようで行ったり来たりしたが。何とか全て回収。
だがおかしい?2番がかぶっている。そして4番が足りない…。
おそらく一方の2番は4番のことだろうとあたりをつけて、集めた文字を並べてみる。
できたワードは「下北沢KOEBOE」…なんのこっちゃ?
当てはめ方が悪かったのかと見直すが、こうにしかならない。
そこで哲郎君、「僕、下北沢巧房(こうぼう)って所なら知ってます!」
うーん…た…多分そこだろう!てか他にアテないし行ってみるしかない!
ちょっと違ってたのは天狗の意地悪だろう!
問題にノイズを混ぜるとはちょこざいな!
結果的にこれはバグだったのかどうかわからなかった。
集めて終わりってのもなんだし、多少のノイズは逆にありかもしれない。
でもどちらかというとNPCである哲郎くんがいなければ、
下北沢巧房を知らない我々としては困ったろう。
「下北沢KOEBOE」でググっても、当然見つからなかったろうし。
もちろんいること前提の問題だったのだろうと思うが、
できればNPCの助言を必要としない問題の方がベターだろう。
急いで「下北沢巧房」に向かう。レンタルボックス屋さんのようだ。
レンタルボックス内に何か不審なものでも置いてあるのか…?と思ったが、
Kが店の人に天狗からの問題文を見せたところ、天狗印のついた封筒を出してきてくれた。
そっちかよw
封筒には「下北沢天狗まつり秘密文書」が入っていた。

真竜寺の天狗の逸話と、天狗まつりの由来についてだ。
最後の「昭和40年の冬の終りのこと…」という意味深な一文が目を引く。
どうやら他のチームも何か見つけているらしい。
事前に教えてもらっていたメーリングリストで続々と情報が届く。
全チームで連携を取る必要があったため、メーリングリストは必須だった。
しかし、それぞれのチームがメールを送り、それが全員に届くため、
慣れるまでは携帯に立て続けにメールが来て、情報は錯綜気味だった。
また、状況把握と問題を説くことに集中できなかったのも確かだ。
要領がわかっていれば、チームで役割分担をすることで
もっとスムーズに捜索できただろうが、
ARGが非現実感を味わうものである以上、
あまり事前に周到な準備をしているのも不自然だ。
そのうちARG慣れしている人間が増えると、メタ行動が増えてしまって、
慣れていない人間との「攻略格差」みたないものを生み出すのではないか?
などという不安も今後は考えられる。
ビデオゲームやボードゲーム、サバゲーなども
すでに同様の問題を抱えている以上、
ARGもこの問題を解決するための対策を今から考えておく必要がある。
祐介からのメール。一度真竜寺に集合して、
それぞれ得た情報を突き合わせよう、とのこと。
急ぎ真竜寺にとって返す。
真竜寺に戻ると、Dチームがなにやら苦戦中。
聞けば暗号の指定ポイントは真竜寺だったらしく、
さらなる暗号を解いて、真竜寺境内に隠された何かを見つけなければならないようだ。
しかもその場所は、ある場所からの「歩数」で示されており、ダミーが大量に混じっているという。
「歩数」の基準(歩幅)自体が曖昧だし、正解もわからないので苦戦しているのだ。
罫線の引かれた紙などで工夫しているが、はた目で見ても難しそうだ…。
仕方が無いので他のチームは暗号によらず、真竜寺境内をしらみつぶしに捜索する。
だが大して広くはない境内だというのに、それらしいものは全く見当たらない。
やや途方に暮れ気味になり、時間が過ぎていく…。
そこで私はふと思い当たって、あるところを調べてみた。…あった。天狗印の巾着袋。
正面入口とは別にあった、閉ざされた門の外側にあったのだ。
一度外に出て回りこまねば辿り着けない。これはなかなか厳しい。
この歩数の問題、ビデオゲームのRPGなどでは定番だが、ARGでは厳しい。
歩幅の誤差は多少とは言え、歩数を増せばかなり大きくなる。
正解がどうだったのかはわからないが、私はメタ思考(問題を出す側の思考)で
辿り着いている(簡単に見つかってしまう普通の場所にはないはず)ので、
正当な正解とは言い難い。
自由度の高さの証左でもあるので、アリっちゃアリかもしれないが。
お寺の寄り合い所のようなところをお借りして、急ぎ情報共有会を始める。
沙織の姿が見えないと哲郎君が気づく。同行したチームによると、どこかに寄ってからくるとのこと。
我々Cチームはまだ沙織に会っていない。どんな子なんだろう?
ところで集まった情報は天狗まつりに関わる文書とどこぞの駐車券、下駄などで、
どう読み解いたものやらさっぱりだ。
しかしDチームの文書(先ほど境内で見つけたやつだ)には何やら不吉な事が。
かつて天狗まつりが革新性を失った時、元気の良い女の子が行方不明になり、
天狗の神隠しだと恐れられた事があったという。
その内容を聞いている皆の脳裏に、沙織のことがオーバーラップしているのか、じわっと不安な空気が漂う。
文書を読み上げていた女性も、最後に「沙織さん大丈夫でしょうか…」と心配そうに呟いた。
「沙織さんも元気な人ですよね」
誰かがポツリと言うと、哲郎君が
「そうですね…アハハ…」
と返すが、声に先程までの元気がない。
その時、私の後ろの襖が突然ガタガタッ!と音を立てた!
…お寺の方だった…。ビックリさせないでくれよ…。
この時は本当にビビったw
まさか瀕死の沙織登場か?!
などとメタ思考していたが、話の筋的にあるわきゃない。
その位ビックリしたという事だorz
しかし待てども沙織は戻らない。皆ポツポツ意見を述べるが、まとまる訳も無い。
そんな最中私の隣の人に電話が。すぐ切られて怪訝な顔をしている。
すると直後に私の携帯にも電話が。知らない番号だ。出てみる。
「ヘッヘッヘッヘッヘッ…」
ブツッ…ツーッツーッ…。…切れた。
何だ?隣の人と同じように怪訝な顔をする私に、Kが何事かと尋ねる。
「いやぁ…なんか変な笑い声だけして切れちゃっ…」
と言っている間にも他の人の所に次々と電話が。
ざわめき立つ皆に確認すると、どうやら同じような状況らしい。
「その番号にかけ直してみて下さい!天狗からのメッセージみたいです!」
いち早くかけ直した人がいるらしい。復唱して内容を書き留めている。
どうやら5カ所に巾着袋を隠したので探せ、との内容らしい。
早く探さないと沙織はどうなっても知らないとも…。
どうやら沙織を人質に取られたのは間違い無いようだ。
天狗に振り回されっぱなしだが、仕方が無い。
各グループ散会して捜索に向かう。俺達の担当は…ビレバン?
「ヴィレッジバンガードだよ」
あ~…。Kに言われてやっと把握する。そんな略し方するとは初耳ですよ。
ヴィレバンの前は人が多い。
ごちゃっとした雰囲気のためかなかなか見つからない。
見つけた他のチームに巾着袋の特徴を聞いたりしていたその時、
哲郎君とKが見つけてくれたようだ。中身は?!
…また暗号か。
どうやら今まで見つけた他の文書がヒントとなって解けるらしい。
内容を覚えていたKがいち早く解答を導き出すが、
これも他のチームの暗号や解答と組み合わせないと意味を持たないようだ。
メールではらちがあかないので、また真竜寺に戻る。
戻るとすぐに答えは出た。さっきの駐車券の駐車場の場所を示していたようだ。
実はこの駐車場の場所は、駐車券に書いてあった名前で
Googleマップを検索した人がいてすでにわかっていた。
だが、ちゃんとスジを追おう、というゲーム慣れした人が多かったので、
駐車券の事は保留になっていたのだ。
こういった事態にも今後のARGは対処していく必要があるだろう。
仮に今回、あのまま巾着袋の暗号をスルーして駐車場に向かっていたら、
どうなっていたのだろうかは興味深い。
大筋に影響はないのでそのまま進んだのだろうと思うけど。
今度は全員で駐車場に向かう。大行軍だなぁw
この辺は、ほとんど車の通りの無い下北の地の利を生かせた部分だろう。
他の街ではなかなかこうは行かない。
駐車場に到着。一番奥の車の中に沙織を見つけたと声が上がる。
確かに女性が中で意識を失っているようだ。彼女が沙織か。
車のドアは幸いカギがかかっていなかったようだ。哲郎君が沙織を揺り起こす。
「あ?どうなってんのコレ?!」
目覚めた彼女はすっ頓狂な声を上げる。
確かに元気な子だなぁ~…などと思っていたら、
なんと手錠でハンドルに繋がれてしまっているらしい。

「五郎よ!五郎の仕業だったのよ!」
手錠の事はとりあえず諦めたのか、何か哲郎君に叫んでいる。
五郎?どなたでしたっけ?
「落ち着いて皆に説明してくれよ…」
祐介に諭されて、沙織は説明を始めた。
天狗が暗号等に使っていたマークに、沙織は見覚えがあった。
委員会の一人、吾郎がデザインしたはずのものだ。
五郎ならば何か知っているかと思い会いに行ったところ、拉致されてしまったのだ。
慌てながらも事情を説明する沙織に電話が…。どうやら五郎からのようだ。
漏れ聞こえる内容から、五郎が近くにいるらしい
…ていうか近くから電話と同じ声が聞こえるような…?
なんと駐車場の下の道に、天狗の面をつけた男の姿が!
こいつが「天狗=五郎」か!
しかしフェンス越しなので近づくことができない!
五郎は我々を挑発し、走り去る。
すぐさま哲郎君が「追いかけましょう!」と駆け出す。
どうやらグループ別に違う道を回ってはさみうちにするらしい。
Cチームは哲郎君と一緒に五郎の後を追う。
ちょ…w哲郎君全力ダッシュっすかwオジサンしんどいっすw
駐車場の付近は住宅街で坂も多い。
…まさかこんなところで全力坂をやることになろうとは…。
一度見失うもののなんとか五郎を確保!捕まえたのは哲郎君でした。
いやいや…こっちはついていくだけで必死でしたよ…。
五郎は捕まった後もヘラヘラと何かを語っている模様。
たまに逃げる素振りを見せながらも、比較的おとなしく連行されていく。
メールで全員に五郎を確保したことを伝え、再度駐車場に集合することに。
駐車場に戻り、五郎の持っていた手錠の鍵で沙織を解放。
五郎は今回の騒動の動機を語りだした。

彼は天狗まつりを盛り上げるために、この騒動に近いイベントを提案したものの、
保守的な実行委員会は相手にせず、ならば、と自分の手でそれを実行してやったんだ、という。
「お前らだって俺が出した謎を解いたり、俺を捕まえるために走ったりした時、
『楽しい』って思ったろ?!」
五郎は我々に問いかけた。確かに楽しかったなあ。
犯人を捕まえるなんてシチュエーション、ゲームでしか体験したことないものな。
そう、特に最後の捕物は、クライマックスを盛り上げる
イベントとして素晴らしかった。
ARGがビデオゲームに大きく優っているのは、
身体性のあるインタラクションなのだから。
自分の体を使うというのは、得られる生々しさが段違いだ。
Wiiですら足元にも及ばない。
特に「走る」という行為は、自然に興奮や達成感を高めてくれる。
この走るというイベントを、途中ではなく
最後に持ってきた配置も絶妙だったと言えるだろう。
彼は彼なりに天狗まつりを盛り上げたかったのだ。
彼の言葉に感ずるところがあったのか、祐介・哲郎・沙織は、
五郎の企画をもう一度委員会にかけあってみよう、と提案する。
ちょうどこれから委員会の会議があるんだそうだ。
そうして、4人は車に乗り込み、我々に別れを告げて去っていった。

めでたしめでたし。
で、俺たちどうすんの?と思っていると、
参加者の中から2人が漫才の出囃子のように前に出た。
「ハイ、どうもお疲れさまでしたー!」

なんと彼ら2人は「シモキタストーリー」の運営側の人間だったのだ!
うん。本当に気づかなかったよ。Kはイベント中、学生服の方の彼と話していたが、
「学生さんだからか初々しくていいね~」などと言っていたほどだ。
まんまと騙された。俺たちもまだまだだな…。
おみやげに、イベント内でも使われていた天狗ステッカーをいただいて解散とあいなりました。
私とKを含めた、興奮覚めやらず語りたいメンバーは、その後下北の夜の街に消えて行ったとさ。